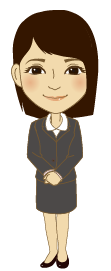
今もなお生前対策として活用される「遺言書」ですが、その役割について詳しい方は多くはないのでしょうか。
遺言書とは、自分の財産を誰に渡したいか、ご自身が亡くなった後の意思表示をするための手段です。遺言書を作成するにあたり、定められた要件を守って作成しなければ、せっかく作成した遺言書も無効となってしまいます。遺産分割を円滑に進めるために要件を満たした遺言書を作成していきましょう。
遺言書にはどんな種類がある?
一般的に遺言書は2種類あります。1つが、遺言者自らが自筆で作成する「自筆証書遺言」と、もう1つが公証役場で立会いの下、作成する「公正証書遺言」の2種類です。その他にも内容を秘密にしたままの「秘密証書遺言書」や、特別な方式による遺言書が存在しますが、あまり一般的ではないではないです。
遺言書は、必ずしも作成する必要はなく、相続手続きを遺言書なしで進めることは可能ですが、遺産相続では遺言者の意思が最優先されます。遺言書の有無は今後の手続きに大きく左右され、遺言書があると、遺言書に沿っての遺産分割を行うため、遺産分割協議を省略することができ、相続人同士のトラブルを避けることができます。よって、相続が発生したらまずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。
遺言書はどこに保管される?
遺言書を保管する場所は様々ありますが、最も多いのがご自宅での保管です。ご自宅以外ですと、自筆証書遺言保管制度を活用した法務局保管や(公正証書遺言の場合は)公証役場に保管されている場合もあります。ただし、法務局にて自筆証書遺言を保管してもらう際は手数料が必要となるので気を付けましょう。
遺言書を開封するときに気を付けること
相続が発生し遺言書を探している最中に、ご自宅から自筆証書遺言らしき遺言書を発見した場合、その場での開封は厳禁です。発見した者が遺言書の内容を改ざんする恐れがあるため、法律内で、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きをしなければ開封できないと定められています。
ちなみに、法務局で保管された自筆証書遺言や公正証書遺言は検認が不要です。
遺言書がない相続手続きは、相続人調査から相続財産調査、そして相続人全員が参加する遺産分割協議を経て、遺産の分割方法を決めていかないといけません。それに対して、遺言書がある相続手続きは、遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容通りに遺産を分割することが可能です。
しかし、遺言書にない財産が発見された際は、その財産にのみに対して協議を行い、分割方法を決めなければなりません。相続人同士のトラブルのもととなる遺産分割協議を極力避けるためには、遺言書があったとしても相続人調査と財産調査は必ず確実に行うようにしましょう。
また、遺言書の内容によっては、遺産の管理や処分を行う権限を持つ者(遺言執行者)を遺言者が指定していることもあります。この場合は、遺言執行者以外の者が遺産の分割や名義変更を行うことは禁止されているので、遺言執行者の記載がある際は、迅速にその方と連絡を取るようにしましょう。
遺言書には遺産分割の意向を記載
遺言書を作成する意味として、遺言者自身が亡くなった際、財産をどう残すのかの方針を自分で決めることができる点にあります。前述したように、相続分割の優先順位は、遺言書が最も最優先となり、その次に遺産分割協議が続きます。
生前対策の一つとして、有効な遺言書は、相続人以外の人へ財産を渡したい、婚姻関係のないパートナーへ相続したい、など相続関係が複雑になる恐れがある場合におすすめの手段です。
遺言書の作成を考えている方の多くは、費用がかからず、自分が好きなタイミングで作成ができる自筆証書遺言を選ぶ傾向がありますが、書き方に多くの要件があるので、作成しても要件を満たしていなければ、せっかくの遺言書が無効となってしまいます。
その反面、費用は多少発生しますが、専門知識のある公証人が作成をする公正証書遺言の方が確実な手段となります。
遺言者の意思をきちんと届けるために、公正証書遺言の作成を長崎遺言相続手続きセンターではおすすめしています。










